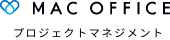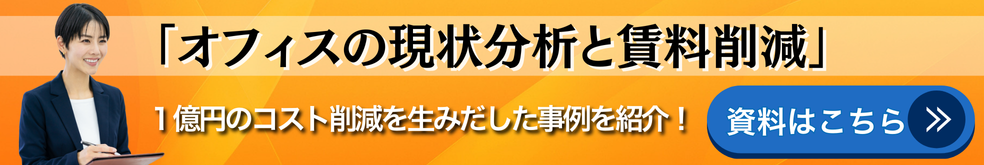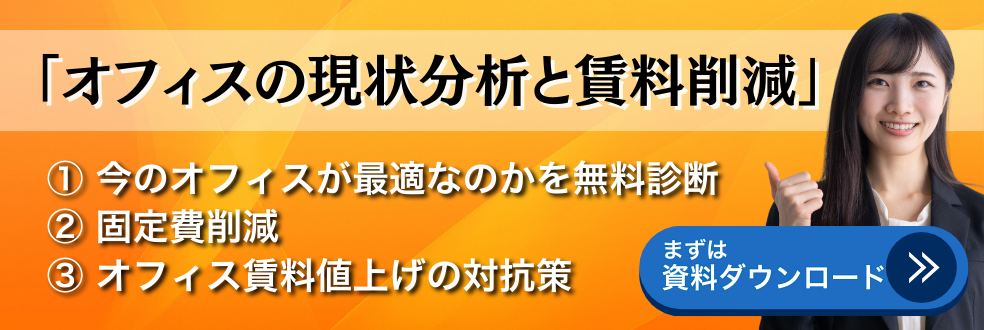財務諸表の数値を分析すれば、企業の経営状況や財政状態を客観的に判断できるだけでなく、現状の課題や改善点なども発見できます。持続的成長を目指すには、財務諸表分析は不可欠です。今回は、財務諸表の主要な分析手法や、分析で用いる計算方法を解説します。
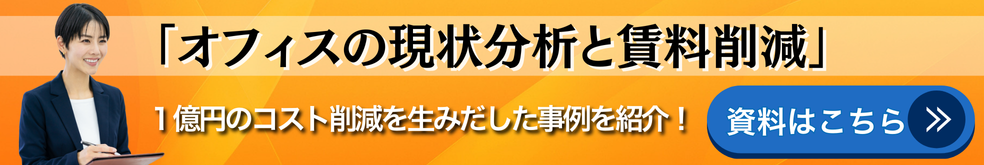
財務諸表分析の重要性

財務諸表分析は、一般的に決算書と呼ばれる財務三表(賃借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書)の数値から、企業の経営状況を判断することです。企業の財務状態に問題がないか、効率良く収益を上げられているかなど、さまざまな情報が得られます。
財務諸表分析は、現状を改善して成長を目指すための有効な手段です。分析により、企業が抱える課題が明らかになり、経営戦略見直しの契機となることも多くあります。
なお、財務諸表分析の対象は自社だけではありません。新規取引先に対する安定性や倒産リスクの判断にも活用可能です。
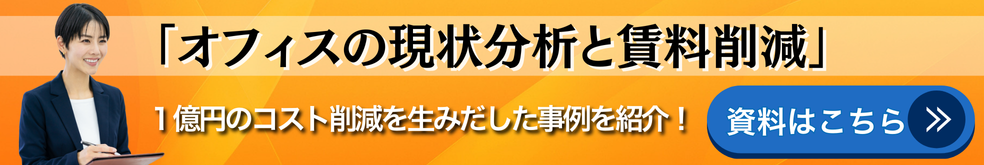
財務諸表の主要な分析手法

財務諸表分析の主な手法には、収益性分析・安全性分析・成長性分析・生産性分析の4つがあります。それぞれの分析の目的や、分析からわかることを解説します。
収益性分析
収益性分析は、企業がどれだけ利益を生み出せる力があるかを分析する手法です。経営状態や事業戦略の適切性を把握できます。
収益性は、売上と資本の2つの観点から分析します。それぞれの主な指標と計算式は以下の通りです。
【対売上高】
| 売上高総利益率(粗利率) |
売上高に対する粗利益の割合で、商品やサービスの収益性を示す |
売上総利益(売上高-売上原価)÷売上高×100 |
| 売上高営業利益率 |
売上高に対する営業利益の割合で、営業力を示す |
営業利益(売上総利益-販売費および一般管理費)÷売上高×100 |
| 売上高経常利益率 |
売上高に対する経常利益の割合で、財務活動を含む収益性を示す |
経常利益(営業利益+営業外収益-営業外費用)÷売上高×100 |
【対資本】
| 総資本経常利益率 |
すべての資本を用いて上げた利益の割合。資産運用効率や経営の健全性を示す |
経常利益(営業利益+営業外収益-営業外費用)÷総資本×100 |
| 株式資本経常利益率 |
株主の出資から上げた利益の割合。収益性や資本運用効率性を示す |
経常利益(営業利益+営業外収益-営業外費用)÷自己資本×100 |
| 経営資本営業利益率 |
本来の営業活動に使う資本から上げた本業の利益の割合。本業の収益性を示す |
営業利益(売上総利益-販売費および一般管理費)÷経営資本×100 |
安全性分析
安全性分析とは、企業の短期的・長期的な支払能力を分析する手法です。財務の安全性や資金調達の健全性により、資金ショートによる倒産リスクや長期的に事業を継続できるかを判断できます。
分析に使用される主な指標には、1年以内の短期的な支払能力を判断する流動比率・当座比率と、長期的な支払能力を判断する負債比率・固定比率があります。
| 流動比率 |
短期支払能力を測る指標。200%以上あれば短期的な支払いに問題がないとされる |
流動資産÷流動負債×100 |
| 当座比率 |
換金性の高い資産から短期支払能力を測る指標。流動比率よりも短期的な支払能力を示す |
当座資産÷流動負債×100 |
| 負債比率 |
自己資本で支払える負債の割合。比率が低いほど経営の安定性が高い |
他人資本÷自己資本×100 |
| 固定比率 |
固定資産をどれだけ返済不要な自己資本でまかなえるかを示す指標。100%以下で安全性が高いと判断できる |
固定資産÷自己資本×100 |
支払能力を上げ経営の安全性を向上させるには、固定費の削減が有効です。固定費削減については、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:「固定費を削減する方法とは|メリットや削減時の注意点を解説」
成長性分析
成長性分析は、一定期間内において企業がどれだけ業績を伸ばしているのかを測る分析方法です。企業の将来性を判断したい際に利用します。
成長性分析の主な指標には、売上高成長率・経常利益成長率・総資本成長率があげられます。それぞれの概要と計算方法は以下の通りです。
| 売上高成長率 |
前期に対する売上高の伸び率。市場での競争力やシェア拡大を示す |
(当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100 |
| 経常利益成長率 |
前期に対する経常利益の伸び率。収益構造が効率的かを示す |
(当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100 |
| 総資本成長率 |
前期に対する総資本の伸び率。企業規模の拡大を示す |
(当期総資本-前期総資本)÷前期総資本×100 |
成長性分析の結果を扱う際には、売上・利益・資本の関係性に着目することが重要です。
例えば、成長性を判断するには、売上高が増加しても、収益が減少しているケースもあるため、売上高成長率とあわせて分析する必要があります。
また、総資本成長率が上昇していても、負債比率が上昇しているケースや売上が増加していないケースもあるため、安全性分析など他の分析も行い、原因を把握することが大切です。
生産性分析
生産性分析とは、企業が投入する労働力や資本などの経営資源から得られる生産物の量によって、生産性を分析する手法です。
生産性分析を行う際には、企業が生み出す経済価値を表す付加価値を用います。付加価値の計算方法には、控除法(中小企業方式)と積上法(日銀方式)がありますが、一般的には控除法が用いられます。
控除法:付加価値=売上高-外部購入費用
積上法:付加価値=経常常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課
生産性分析に用いる主な指標には、労働生産性・労働分配率があげられます。
| 労働生産性 |
従業員1人につき得られる付加価値 |
付加価値額÷従業員数 |
| 労働分配率 |
付加価値に占める人件費の割合 |
売上総利益÷人件費×100 |
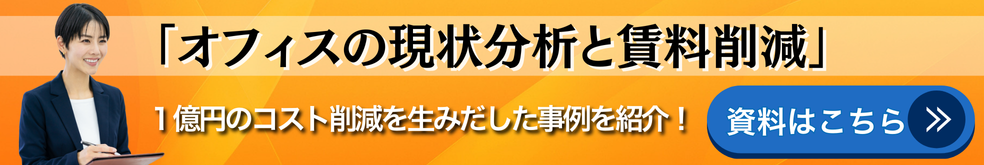
財務諸表分析における計算方法

財務諸表分析は、財務諸表の実数を用いる実数分析と、実数から求めた比率を用いる比率分析の2つの方法で行います。それぞれの分析方法と、分析で得られることを紹介します。
実数分析
実数分析は、財務諸表に記載されている売上や経費などの数値(金額)をそのまま用いる分析手法です。売上高や販売数量など、量について時系列や業種平均値と比較・分析したい場合に適します。実数を用いるため、直感的に分析結果を把握できることが特徴です。
実数分析を用いる分析には、以下があげられます。
・売上・利益増減分析
・原価差異分析
・経常収支分析
・キャッシュフロー分析
比率分析
比率分析は、財務諸表の実数から求められる比率を用いた分析方法です。
実数分析は量の分析に適しているのに対して、比率分析は質の分析に適しています。事業の収益性や安全性などの数量では可視化できない要素を、客観的に把握可能です。財務諸表の主要な分析手法で紹介した4つの手法では、いずれも比率分析を用います。
また、実数分析では難しい規模が異なる企業間の比較も、比率分析を併用することで可能になります。
なお、比率分析は財務状況を把握できるだけでなく、戦略的な意思決定にも活用可能です。具体的には、収益性や安全性の分析からコスト構造の見直しや、新規事業への投資判断、資金調達計画の策定などを検討できます。
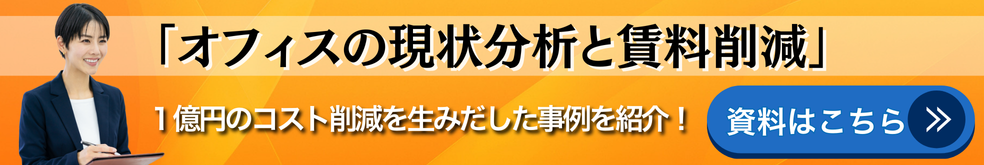
まとめ
財務諸表分析は、企業の財務状況を正しく把握するための重要な手段です。また、さまざまな意思決定や将来的な経営戦略の策定にも活用できます。目的に応じた分析手法で、定期的に分析を行いましょう。
財務状況の改善や固定費削減の手段には、ダウンサイジング移転によりオフィス賃料を削減する方法もあります。費用を削減できるだけでなく、社員同士の交流の活性化や新しい働き方を推進し、企業価値の向上にもつながります。
ダウンサイジングの事例は、下記で詳しく紹介しています。
>>MACオフィスのダウンサイジング事例(株式会社オレンジページ様)の詳細はこちら
オフィスの見直しをお考えなら、まずは無料のオフィス診断をご利用ください。経営状況や企業課題に応じたご提案が可能です。
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
なお、下記の記事では、オフィス賃料の相場や見直しの基準などを解説しています。あわせて参考にしてください。
「オフィス賃料の相場は?適切な賃料の判断基準や見直し方も解説」
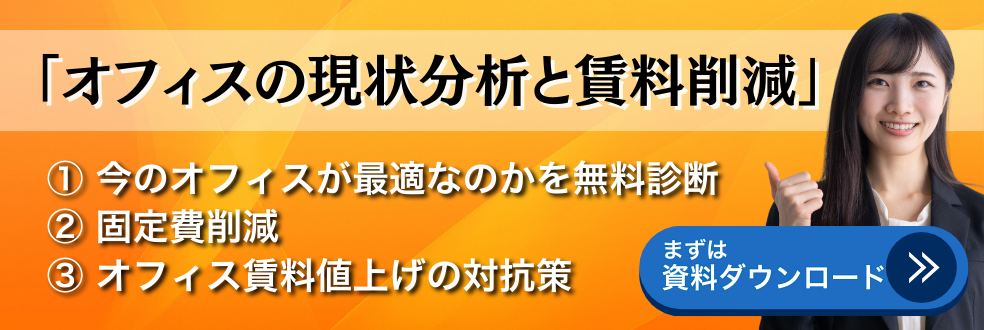
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略組織づくり
経営戦略組織づくり