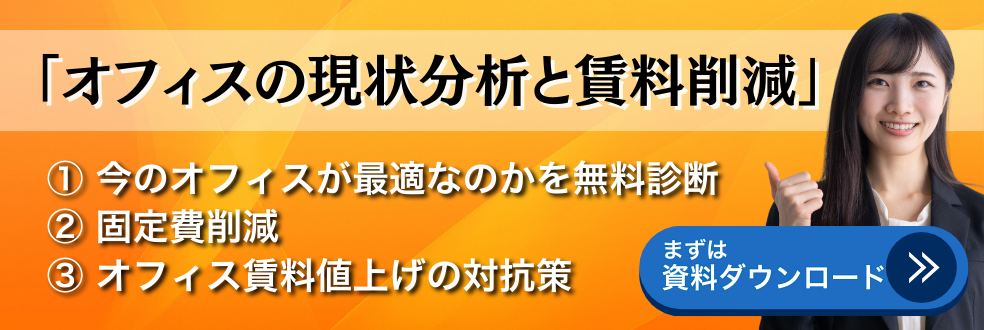経営状態の改善を図るには、固定費や変動費の見直しによる効果的なコスト管理、データに基づく財務状況の分析が欠かせません。こうした収益性の向上を目指すプロセスで必要となる指標が、限界利益や限界利益率です。
今回は、限界利益と限界利益率の計算方法をはじめ、その分析から読み取れる事項、限界利益率を向上させる方法について解説します。
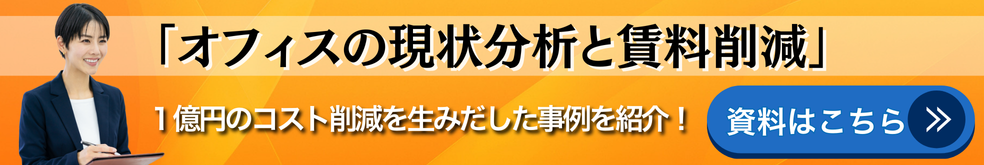

限界利益とは、商品やサービスを販売することで得られる利益を指します。事業が十分な利益を得られているかどうかを見極めるための指標として、価格設定や事業継続の判断にも活用されています。
限界利益は、商品やサービスの売上高から変動費を差し引くことで求められます。計算方法は下記の通りです。
| 限界利益=売上高-変動費 |
ここでは、1個1,000円の商品Aを例に限界利益を算出してみましょう。商品Aの原材料費が1個につき500円発生する場合、1,000円-500円=500円が、商品Aの1個あたりの限界利益です。
商品Aが10個売れれば、500円×10個=5,000円と限界利益も多くなっていきます。仮に変動費が600円に上がれば、商品1個あたりの限界利益は400円に減少します。
限界利益の計算に用いる変動費とは、具体的にどのような費用を指すのでしょうか。事業運営において商品やサービスの提供にかかる支出は、下記の固定費と変動費に分けられます。
固定費は、生産量や販売量、売上高に影響されない費用です。例えば、人件費やオフィス賃料、設備の減価償却費、リース費用、保険料などがあります。企業にとっては、状況にかかわらず、継続的に発生する出費となります。
生産量や販売量、売上高に応じて変動する費用を指します。代表的な変動費は、原材料費、仕入れ費、外注費、運送費などです。変動費の高い商品やサービスは、利益が薄くなる傾向があります。
ちなみに、固定費と変動費に絶対的な区分はありません。例えば人件費の場合、正社員の賃金は固定費に分類されますが、変動する要素のある繁忙期の残業代、アルバイトの賃金などは変動費とも捉えられます。両者を区分する基準は売上に連動するか否かです。
なお、限界利益と固定費が等しくなるポイントは損益分岐点と呼ばれます。損益分岐点は赤字と黒字を分ける境界で、経営判断に欠かせない指標です。固定費や損益分岐点について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:
「固定費を削減する方法とは|メリットや削減時の注意点を解説」
「損益分岐点を算出するには固定費と変動費の分類が重要|損益分岐点を下げる方法も紹介」
限界利益率は、売上高に占める限界利益の比率を示す数値です。商品やサービスが効率的に利益を生み出せているかを評価する際に利用されます。限界利益率は、次の計算式で求められます。
| 限界利益率(%)=限界利益÷売上高×100 |
再度、500円の変動費が発生する1個1,000円の商品Aを例に考えてみましょう。商品Aが1個売れたときの限界利益は500円となることから、限界利益率は、500円÷1,000円×100=50%と算出されます。
変動費が250円に下がり、限界利益が750円になった場合は、750円÷1,000円×100=75%と限界利益率が上昇し、収益もアップします。
なお、限界利益率の平均値は各業界でさまざまです。例えば、小売業では40~50%、建設業では15~30%が目安とされています。
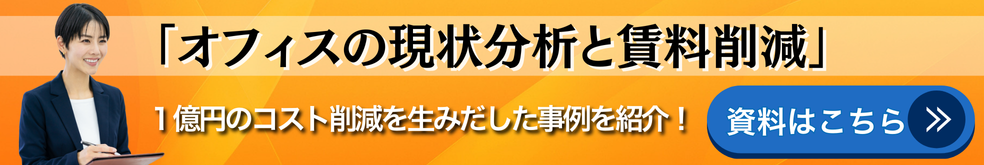

限界利益と限界利益率は、収益力の評価や経営判断に役立つ重要な指標です。価格設定やコスト管理、財務状況の把握、事業の持続可能性の評価など、幅広い場面で活用されています。
限界利益は、数字が大きくなるほど収益性が高いことを示す一方で、数字が伸びていない場合は、効率良く利益を生み出せていないと判断されます。
また、売上に占める限界利益の割合を示した限界利益率は、売上の増加が利益に結びつく度合いとも捉えられます。つまり、限界利益率の高い商品やサービスほど、売上の増加にともなって収益も伸びる関係にあるということです。
限界利益や限界収益率が高ければ、固定費の回収も容易になり、経営状態を判断する上でプラスの材料となります。一方で、低迷している場合は、早期の対策が求められます。
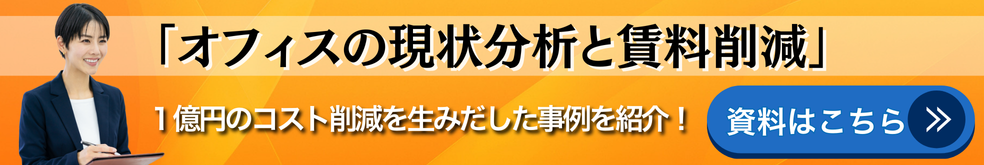

限界利益率を高め、収益力をアップさせるには、大きく3つの方法が考えられます。それぞれの方法を詳しくみていきましょう。
限界利益率を高めるための容易な方法が、商品やサービスの値上げです。変動費を据え置いたまま単価を上げれば、値上げ分が売上につながることから、限界利益の改善が見込めます。
例えば、販売数を増やして売上を伸ばそうと値引きをしているケースでは、値上げによる価格の適正化で、収益が改善されることも少なくありません。過度な値引きが限界利益を下げ、収益を低下させている場合もあるからです。
ただし、値上げは販売数の減少に直結するおそれがあるため、慎重な判断が必要です。商品やサービスの質向上がともなっていないと判断されれば、顧客離れや顧客満足度の低下を引き起こすリスクもあります。
このような状況を踏まえ、限界利益率の向上を目的とした単価アップには、短期的な利益追求だけでなく、長期的な収益も見越した価格設定や品質管理が求められます。
複数の商品やサービスを取り扱う事業では、限界利益率が高い商品やサービスの販売数を増やすことで、事業全体の限界利益が拡大する可能性は高くなります。
販売数を上げる対策として、既存顧客のリピート率向上や新規顧客の開拓が考えられます。下記は、その際に役立つ顧客満足度の向上や認知度アップのための施策です。
・高付加価値の商品やサービスの提供
・応対品質の向上
・クロスセルによる顧客1人あたりの購入点数の増加
・SNSやWeb広告による商品やサービスのPR
・顧客の属性に合わせたキャンペーン
新規顧客からリピーターになる割合が定期的に増えていけば、販売数や売上の向上も望めます。
売上を維持しつつ変動費のみを削減することは、それほど容易ではありません。なぜなら変動費は、そもそも売上高に比例して増減するからです。とはいえ、見直すべきポイントはあります。
まずは、過去の仕入れ数や販売データなどの分析から在庫量を適正化し、原材料のロスを改善することです。商品の製造に必要な量を正確に見積もり、適切な在庫管理を行うことで無駄を省きます。
さらに、仕入れ先の変更や仕入れルートの開拓により、原材料のコストカットを実現できれば、変動費の抑制につながります。
加えて、物流コストの削減も効果的な方法です。物流コストの最適化策として、コスト効率の良い輸送方法の選定、ルートプランニング、契約条件の見直しなどが考えられます。
業務によっては、変動費を占める外注費と内製にかかる費用の割合を見直すのも、ひとつの方法です。ただし、コストだけでなく、品質を維持できるか、ノウハウを保有したいコア領域に該当する業務かなどの観点から十分な検討が求められます。
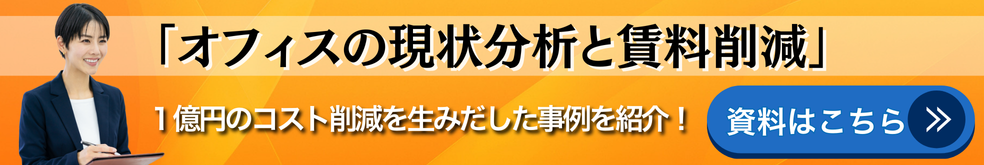
収益を最大化し、企業の持続的な成長を促進するために、限界利益や限界利益率を適切に管理することが求められます。限界利益率を高めるには、価格の適正化をはじめ、高限界利益率の商品やサービスの販売強化、変動費の削減などの方法が有効です。
経営状態の改善という観点では、無理のない範囲で行う固定費の見直しも大きな効果をもたらします。その方法のひとつとして、固定費の一定割合を占めるオフィス賃料の削減があげられます。
MACオフィスでは、オフィス戦略における重要な意思決定や最適なオフィス環境の実現をサポートしています。オフィス移転を前提とするのではなく、シェアオフィス活用やレイアウト変更など、複数の観点からのご提案が可能です。
>>MACオフィスの事例に関する資料ダウンロードはこちら
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
オフィス賃料の値上げに悩む企業様の事例では、適正なオフィス面積や機能性を提案することで、コストを抑えた新オフィスへの移転を実現しています。詳しくは、下記をご覧ください。
>>MACオフィスのビルグレードアップ・ダウンサイジング移転事例の詳細はこちら