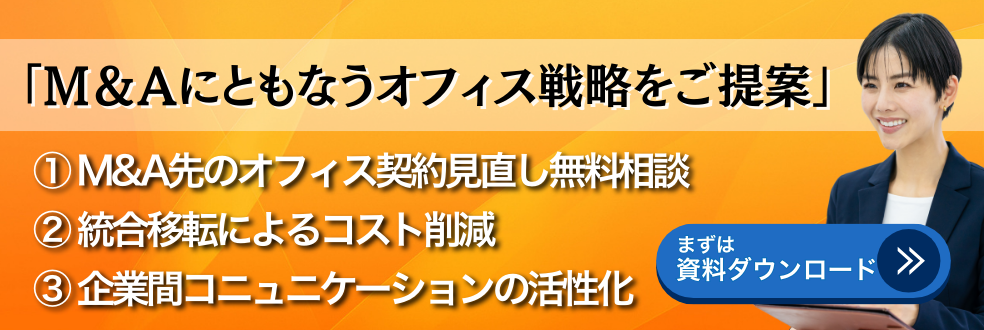M&Aの検討にあたって、M&Aにともなう費用のサポートについて知りたいと考えていませんか。M&A関連では、旧:事業承継・引継ぎ補助金として知られた「事業承継・M&A補助金」があります。今回は、事業承継・M&A補助金の概要と申請の流れ、審査のポイントについて解説します。
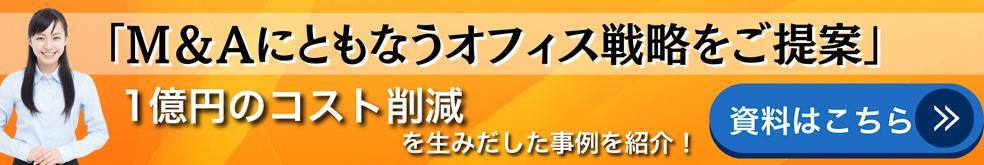

事業承継・M&A補助金は、中小企業向けに、持続的な賃上げや生産性向上を目的に、事業承継をサポートするための補助金です。M&Aや事業承継にともなう設備投資、PMI(経営統合)の専門家への費用をサポートするもので、2025年度中に募集が実施される予定です。
なお、旧制度の2024年度の「事業承継・引継ぎ補助金」では、1月、3月、7月の年3回に分けて公募がありました。昨年度までの傾向から、2025年度に名称を変更して公募が始まる「事業承継・M&A補助金」は、年2~4回の公募が予想されています。
詳細については、事業承継・M&A補助金の公式ページをご確認ください。
※上記およびこれから紹介する情報は、2025年1月時点までに公開されている2025年度分の公募情報をもとにしたものです。
出典:
事業承継・引継ぎ補助金事務局「事業承継・引継ぎ補助金」
中小企業庁「事業承継・M&A補助金で」
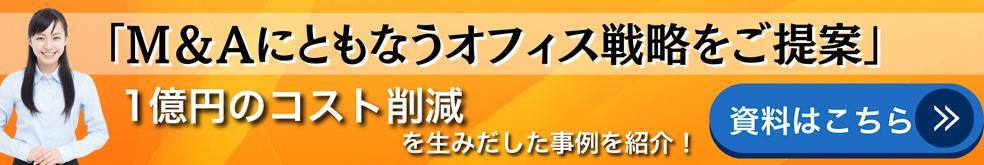

令和6年度補正予算に組み込まれた事業承継・M&A補助金には、4つの支援枠が設けられています。それぞれの支援枠の特徴を解説します。
事業承継促進枠(経営革新)は、親族または従業員への承継を5年以内に予定する事業者を対象とした支援枠です。事業承継を円滑に行うための設備投資や関連する費用について補助を受けられます。
補助上限:800万円~1,000万円
補助率:2分の1または3分の2(小規模事業者に該当する場合)
対象経費:設備費、外注費、委託費など
出典:中小企業庁「事業承継・M&A補助金で」
専門家活用枠は、M&Aで専門家に仲介などを依頼する際の費用を補助する支援枠です。経営資源の譲渡を受ける事業者、または譲渡する事業者を対象とします。補助対象になる専門家への費用は、M&A支援機関登録制度に登録のあるフィナンシャル・アドバイザーや仲介業者に限定されます。
補助上限:買い手支援は600~800万円または2,000万円(100億円企業の要件に該当する場合)、売り手支援は600~800万円
※800万円を上限にデューデリジェンス費用の申請をする場合は200万円を加算
補助率:買い手支援は3分の1・2分の1・3分の2(赤字などの場合)、売り手支援は2分の1または3分の2(赤字などの場合)
対象経費:謝金、委託費、システム利用料など
出典:中小企業庁「事業承継・M&A補助金で」
PMI推進枠は、PMI(経営統合)を進めるためのM&A後の費用をサポートする支援枠です。旧補助金には存在しなかった支援枠で、2025年度の補助金で新設されました。M&Aで経営資源の譲渡を受ける予定の中小企業などのPMIの取り組みを行う事業者が対象です。
補助上限:専門家活用類型は150万円、事業統合投資類型は800~1,000万円
補助率:専門家活用類型は2分の1、事業統合投資類型は2分の1または3分の2(小規模事業者に該当する場合)
対象経費:設備費、外注費、委託費など
出典:中小企業庁「事業承継・M&A補助金で」
廃業・再チャレンジ枠は、M&Aや事業承継により廃業する事業者の関連経費を補助する支援枠です。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠(事業統合投資類型)と併用できます。
補助上限:150万円
補助率:2分の1または3分の2
※併用の場合はそれぞれの支援枠の補助率に従います。
対象経費:在庫廃棄費、解体費、移転・移設費(併用の場合のみ)など
出典:中小企業庁「事業承継・M&A補助金で」
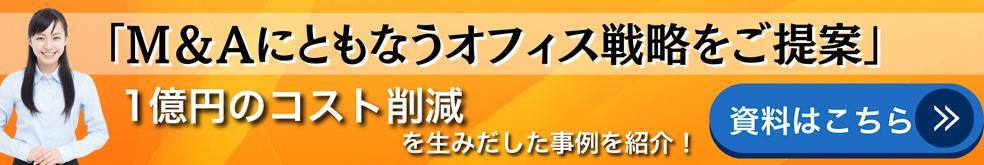
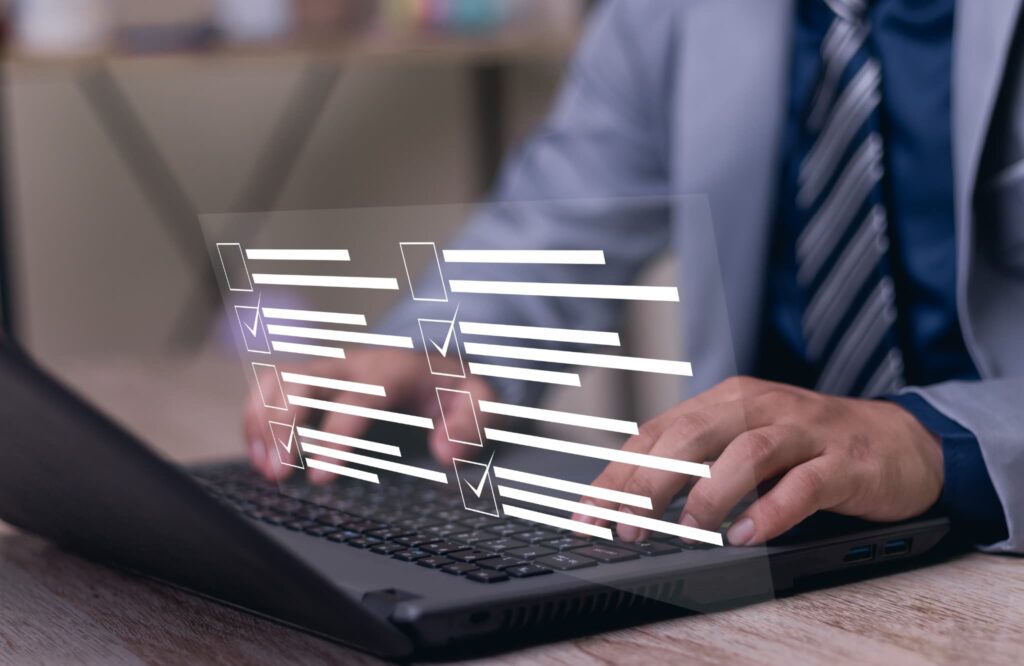
事業承継・M&A補助金を申請する大まかな流れを、6ステップに分けて紹介します。
自社の事業が、事業承継・M&A補助金の補助対象になるかどうか、事前に公募要領を確認します。補助対象事業者や申請する支援枠や類型の理解を深め、事業承継・M&A補助の申請を検討しましょう。
事業承継・M&A補助金で応募する申請枠を把握した後は、公募要領から要件を確認します。対象事業者であることのほか、対象事業であるか、補助金の目的である事業承継を満たすかどうかの確認が必要です。
次に、gBizID(ジービズアイディー)プライムのアカウント発行の手続きを行います。gBizIDは行政サービスの認証システムのことで、gBizIDプライムは事業者向けのアカウントです。
申請から発行までは、通常であれば1週間程度ですが、2~3週間程度時間を要する場合もあります。応募できる期間から逆算して、早めの手続きが必要です。なお、gBizIDプライムのアカウントを作成するにあたり、下記の書類の提出が求められます。
・申請用のデバイス(PCなど)
・事業者のメールアドレス
・SMS受信に対応したスマートフォンなど
・登録印
・発行から3か月以内の印鑑証明書の原本
gBizID取得後は、jGrantsにアクセスします。jGrantsは、補助金を電子申請により受け付けているサイトです。申請する支援枠に応じて必要な書類を事前にそろえた上で、申請手続きを進めます。必要書類は、申請までに公募要領で確認しておきましょう。
申請後、中小企業庁や事務局のページで交付決定者の公表が行われます。jGrantsでも採否の通知が届くため、交付決定スケジュールを確認しておきましょう。
交付決定の通知を受けた事業者は、補助対象事業を実施し、完了後に事務局に実績報告を行います。なお、補助対象事業であっても、対象期間に該当しない契約や支払いについては補助対象経費にはできません。
また、相見積もりが必要な場合に行わなかった場合も対象外となるため注意しましょう。
補助対象事業完了後の実績報告の後に精算払いで補助金が交付されます。事業完了の15日以内に実績報告をすることで、事務局で事業内容の確定検査が実施され、内容に問題がなければ補助金が交付される流れです。
なお、補助金の採択を受けた事業者は、補助金の交付後も、定期的に事業化状況報告などを行う必要があります。
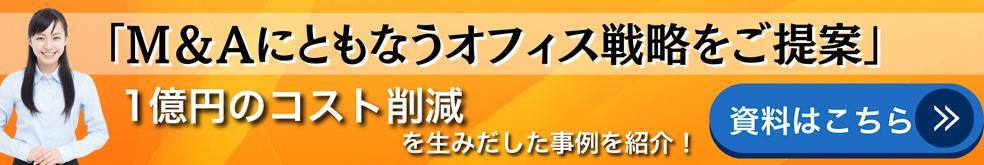
事業承継・M&A補助金は予算の範囲内で行われることから、審査の難易度は高いとされています。旧補助金では、専門家などのサポートを得ても採択率は半数ほどとされています。事業承継を円滑に進めるだけでなく、事業承継の効果などを詳細に審査されることが理由です。
では、事業承継・M&A補助金の審査に通過して採択を受けるにはどうすれば良いのか、旧補助金の状況をもとに採択のポイントを5つ紹介します。
補助金の申請には時間を要します。補助金制度の理解に加え、電子申請のための事前手続き、支援枠ごとの必要書類の準備、支援者との計画策定の時間などが必要になるためです。
特に申請締め切りの間際は、専門家のサポートを受けたいと考えていても、満員により受け付けが終了していることもあります。準備が追いつかず申請を見送るケースもよくみられるため、締め切りまでのスケジュールを確認した上で、余裕をもって準備を進めていくことが重要です。
事業承継・M&A補助金には、複数の申請類型が存在します。審査の対象外にならないためにも、自社の計画に適した申請類型を選択することが重要です。
応募期限までに必要書類をそろえて申請しても、書類に不備があると審査から外れてしまいます。提出書類に記入漏れや誤りがないか、十分に確認した上で申請手続きを進めましょう。
公募要領には審査項目が記載されています。旧補助金では、審査の加点事由として、下記のような内容が記載されていました。
・中小企業の会計に関する指針の適用を受けている
・有効な期間において経営力向上計画の認定を受けている
・中小企業基本法などに規定する小規模企業者に該当する
など
出典:事業承継・引継ぎ補助金事務局「中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 専門家活用枠【公 募 要 領】10次公募」
加点事由などを参考に、補助対象事業のアップデートができないか検討しましょう。
旧補助金では、電子申請の際に計画内容を入力する仕様でした。審査では計画内容も見られています。内容が正しく審査側に伝わるよう、また審査項目に沿って明確に伝わるよう丁寧に記載することが重要です。
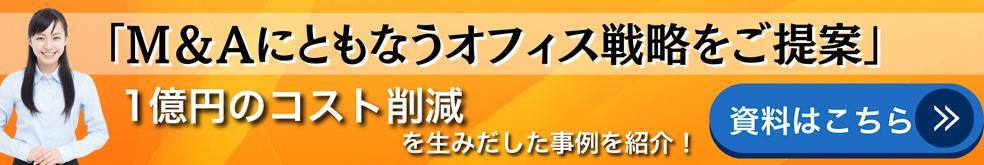
事業承継に関わる費用の補助については、旧名称の事業承継・引継ぎ補助金から名前を変えた「事業承継・M&A補助金」があります。事業承継やM&Aに関する設備費など各種費用の補助が受けられます。
M&Aにともなうオフィス戦略の見直しなら、MACオフィスにご相談ください。MACオフィスでは、オフィス移転やシェアオフィス活用、レイアウト変更など、多方面のオフィス戦略の中から現状を踏まえて提案し、意思決定に至るまで完全成功報酬型で提供します。ご興味のある方は下記からご確認ください。
>>MACオフィスのサービス詳細はこちら
>>オフィスコンサルの事例に関する資料ダウンロードはこちら
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
関連記事:「【買い手側・売り手側】M&Aのメリット・デメリットは?」